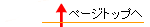※本記事中にはプロモーションが含まれます
DOE(株主資本配当率)の計算方法、仕組み、活用方法
株主から集めた資本金(株主資本)の何%を配当として出せているのかを見るための指標。経営者が株主から預かった資本からどれだけの利益(配当)を出せているのかを見る指標。配当性向と同じように企業の配当に対する姿勢を見るための指標。
DOE(株主資本配当率)の計算方法
計算式(1)
DOE(株主資本配当率)=年間総配当額÷自己資本
計算式(2)
配当性向=1株当たり配当額÷BPS(1株あたり純資産)
DOE(株主資本配当率)が注目される理由
DOE(株主資本配当率)はこれまではあまり注目される指標ではありませんでしたが、近年注目を集めて生きています。
その理由としては、企業の経営効率という面が注目されているという物が挙げられるでしょう。ROE(株主資本利益率)といった株主から預かった資本をどれだけ上手に活用できているかが注目されており、その流れとして、株主から預かった資本に対してどれだけの株主還元ができているかも注目されているという流れのようです。
DOEが高い銘柄の特徴と経営目標とする会社が増えた理由
DOEが高い銘柄はその計算上、「ROEが高い」「配当性向が高い」というどちらか、あるいは両方を満たしている会社と言うことになります。
経営効率がよく株主還元に対する姿勢も良好な銘柄と言うことになります。
いわゆる「配当性向」だけだとあくまでも利益に対してどの程度の分配をするか?という目安でしかなく、100億円の利益を上げた場合と1億円しか利益が出なかった場合とを評価することができません。
ところが、DOEにすると、株主資本に対する利回りも同時に求められることになりますので利益自体も出さないと達成できません。
近年では、こうした特徴から、DOEを経営上の目標指数とする会社も出てきています。
たとえば、従来より配当性向を目標として掲げてきた松井証券は2015年4月よりDOEを7%以上とするという方針を打ち出しています。